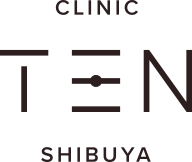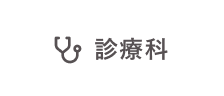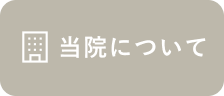内容監修
草壁 広大
KODAI KUSAKABE
草壁 広大
KODAI KUSAKABE
医師/日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医
東京慈恵会医科大学医学部を卒業、国立病院機構 東京医療センターでの初期臨床研修を経て、東京慈恵会医科大学 産婦人科学講座に入局。産婦人科専門医を取得後、同講座の助教を経て、現在は千葉西総合病院産婦人科に勤務。当院では婦人科診療全般の監修および毎週火曜の婦人科外来を担当。
つらい生理痛だけでなく、多い日の経血漏れや生理前にできるニキビなど大きい悩みから小さいものまで女性なら誰しも月経にまつわる悩みを抱えたことがあると思います。それらを改善しうるのが超低用量・低用量ピルです
そもそもピルとは??
ピルはエストロゲンとプロゲステロンという2つの女性ホルモンを合わせた薬です。エストロゲンの量によって超低用量、低用量、中用量ピルに分類されます。
ピルを毎日内服することで避妊効果が生まれます。ピルにより排卵が抑制されるためです。この効果から、ピルは「避妊のための薬」というイメージをお持ちの方も少なくないでしょう。実はピルは避妊効果に限らず、女性のQOL向上のために有益な薬です。
例えば、辛い生理痛や過多月経(月経の回数が多い)の症状がある場合には、ヤーズ、ヤーズフレックス、ルナベル、ルナベルULD錠など保険適応にて処方可能なピルもあります。ご自身の症状に保険適用でピルが使えるかどうか知りたい場合は、お気軽にご相談くださいませ。
また当院の自費診療ではトリキュラー錠28またはマーベロン28を取り扱い・処方しております。
ピルを利用するメリット
ピルを利用するメリットとして
- 月経痛の緩和
- 月経周期の改善
- 高い避妊効果
- にきびの改善
などがあります。またピルの内服は婦人科疾患の予防にもつながります。日本では子宮内膜症といった婦人科疾患の発症リスクが上昇しています。近年の日本で初産の年齢が上昇しており、これにより婦人科疾患リスクが高まっているためです。低用量ピルを適切に使い月経回数を減らすことで、そのような婦人科疾患を予防する効果も期待できます。
ピルを利用するときのデメリット
ピルにはもちろんデメリットもあります。低用量・超低用量ピル内服によるデメリットとして以下のものが挙げられます。
- 費用負担がある
- 血栓症リスクがある※
- 長期服用で子宮頸がんのリスクが上がる可能性がある *子宮頸がん予防接種(9価HPVワクチン)をお勧めしています
- 乳がん発症リスクを増加させる可能性がある *定期検診をお勧めしています
※静脈血栓塞栓症のリスクは下記の通りで、正しく医師の指導の下で内服すれば心配しすぎる必要はありません。
− 内服なし 1-5人 / 10,000人 ・年間
− ピル内服 3-9人 / 10,000人 ・年間
− 妊娠中 5-20人 / 10,000人・年間
− 産後12週まで 40-65人 /10,000人・年間
低用量ピルを内服できない人
- 喫煙している方
- 前兆のある片頭痛のある方
- 高血圧がある方
- 50歳以上、または閉経後の方
- 産後4週間以内の方
- 授乳中の方
低用量・超低用量ピル内服中(前)に必要な検査
- 問診
- 血圧測定
- 超音波検査(初回のみ。月経困難症の原因となる婦人科的病気がないか調べます)
- 子宮頸がん検診(必要に応じて)
費用(税込)
※自費診療の場合
| 初診料 | 2,750円 |
| 再診料 | 1,100円 (2回目以降) |
| 採血料 (肝機能・腎機能・血栓症リスクなどを評価) | 3,300円 |
自費処方薬
| 薬剤名 | トリキュラー錠28 | マーベロン28 |
| 効果・効能作用機序 | 避妊 排卵抑制作用を主作用とし、子宮内膜変化による舟床阻害作用及び頸管粘液変化による精子通過阻害作用等により避妊効果を発揮する | 左に同じ |
| 有効成分 | レポノルゲストレル、日局エチニルエストラジオール | デソゲストレル、日局エチニルエストラジオール |
| 製造販売元 | パイエル薬品 | オルガノン |
| 処方価格(税込み概ね1 か月分) | 28錠3,300円 | 28錠2,750 円 |
| 服用方法 | 1日1錠を毎日一定の時刻に、定められた順に従って(赤褐色糖衣錠から開始)28日間連続で内服 | 左に同じ |
| 服用の注意点 | ・毎日一定の時刻に服用すること。 ・経口避妊剤を初めて服用する場合、月経第1日目から服用を開始する。服用開始日が月経第 1日目から遅れた場合、飲みはじめの最初の1週間は他の避妊法を併用すること。 ・飲み忘れ等がないよう服用方法を十分注意する。万一飲み忘れがあった場合(28錠製剤の白色糖衣錠(大)を除く)、翌日までに気付いたならば直ちに飲み忘れた錠剤を服用し、その日の 錠剤も通常どおりに服用する。 ・2日以上連続して飲み忘れがあった場合は服用を中止し、次の月経を待ち投与を再開する。 なお、飲み忘れにより妊娠する可能性が高くなるので、その周期は他の避妊法を使用すること。 | 左に同じ |
| 効果が出る時間 | 服用開始から1 週間程度 | 左に同じ |
| 標準的な治療期間 | 6か月程度から症状や希望に応じて期間が変動する。 | 左に同じ |
| 標準的な治療回数 | 3か月に1 度程度を目安として受診するため、6か月の治僚回数は2回程度。 | 左に同じ |
| 標準的な費用の総計 (6か月の概算金額) | 22,000円程度 | 18,700円程度 |
| 併用注意薬 | 副腎皮質ホルモン、三環系抗うつ剤、セレギリン塩酸塩、シクロスポリン、オメプラゾール、テオフィリン、チザニジン塩酸塩、リファンピシン、バルビツール酸系製剤、ヒダントイン系製剤、カルバマゼピン、ボセンタン、モダフィニル、トビラマート、テトラサイクリン系抗生物質、ペニシリン系抗生物質、テルビナフィン塩酸塩、Gn-RH誘導体、血糖降下剤、ラモトリギン、モルヒネ、サリチル 酸、HIVプロテアーゼ阻害剤」非ヌクレオンド系逆転写酵素阻害剤、フルコナゾール、ボリコナゾール、アセトアミノフェン、セイヨウオトギリンウ含有食品 | 左に同じ |
| 服用禁忌 | ・本剤の成分に対し過敏性素因のある女性 ・エストロゲン依存性悪性腫瘍(例えば、乳癌、子宮内膜症)、子宮頭症及びその疑いのある患者 ・診断の確定していない異常性器出血のある患者 ・血栓性静脈炎、肺塞栓症、脳血管障害、冠動脈疾患又はその既往歴のある恵者 ・35歳以上で1日15本以上の喫煙者 ・前兆(関輝暗点、星型閃光等)を伴う片頭痛の患者 ・肺高血圧症又は心房細動を合併する心臓弁膜症の患者、亜急性細菌性心内膜炎の既往歴のある心臓弁膜症の患者 ・血管病変を伴う糖尿病患者(糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症等)や、血栓性素因のある女性 •抗少>脂質抗体症候群の惠者 ・手術前4週以内、術後2週以内、産後4週以内及び長期間安静状態の恵者 ・重篤な肝障害、肝腫場、脂質代謝異常、高血圧のある患者(軽度の高血圧の患者を除く) ・耳硬化症の憲者 ・妊娠中に黄疸、持続性そう症又は妊娠ヘルペスの既往歴のある患者 ・妊婦又は妊娠している可能性のある、または授乳中の女性 ・骨成長が終了していない可能性がある女性 | 左に同じ |
| 副作用 | 血栓症、下腹部痛、乳房緊満感、悪心・嘔吐 | 左に同じ |